
近年は世界中で肥満が増加していますが、高血圧や高血糖、動脈硬化などの危険性が高まり、さまざまな病気の原因となるため社会問題となっています。世の中にはさまざまなダイエット方法が知られていますが、「寄生虫によって痩せる」といった方法が昔から知られています。
記事を読む

ある種の古細菌をはじめとする下等動物では、超高温や極低温など極端な環境でも生き延びる能力をもった生物がみられます。我々のような哺乳類はそのような強いからだを持っていませんが、しかし精子に限って言えば、かなりの極限環境にも耐性があるようです。
記事を読む

なるべく効率的に筋力をアップするためにはどのようにトレーニングを行えばよいのか。トレーニングジムや書籍、あるいはネットメディアなどでさまざまな情報が手に入りますが、トレーニングの「セット数」は注目される話題のひとつです。
記事を読む

健康な歯を保つことと全身の健康との関係が指摘されていますが、最近の研究からは健康な「歯の本数と睡眠時間」の関係が明らかになっています。なるべく多くの歯を残すことが、適切な睡眠を維持することにつながるようです。
記事を読む

小鳥がさえずる「歌」を子孫に伝える脳の仕組みが解明されています。いったいどのようにして、外界の関係ない音と区別して親が歌う歌だけを模倣しているのでしょうか。
記事を読む

日常の食生活にほとんど「魚」を取り入れていない人は、大動脈疾患による死亡リスクがおよそ2倍にも増加してしまうことが明らかになりました。そして、月に1回から2回程度食べていればリスク増加を防げることもわかりました。
記事を読む

パソコンやスマートフォンをよく使っていたり、あるいはコンタクトレンズの装着時間が長くなると目の疲れに悩まされることがあります。とくに「ドライアイ」になってしまうと目の表面に傷がついているケースもあるため、早めに診断をして対処する必要があります。
記事を読む

記憶力を高めて効率よく学習をするためには睡眠が大事だということはよく言われていますね。ではいったいなぜ睡眠が必要なのか。そこには記憶を高める「クールダウン」のメカニズムが存在することが脳の研究から明らかにされています。
記事を読む
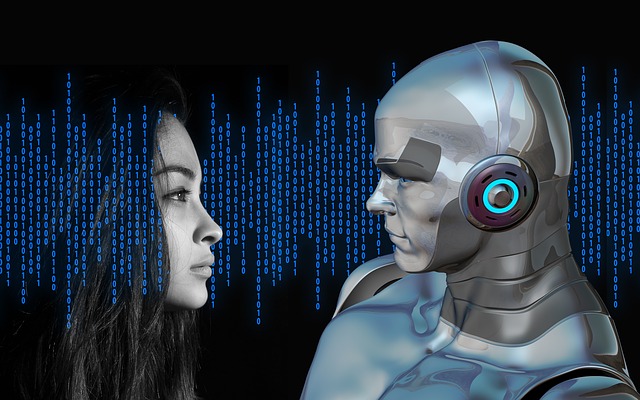
脳波を計測してアンドロイドを操作するブレイン・マシン・インターフェースによって、「3本目の腕」を動かすことに成功しています。自分の腕を使いながら別の腕も使えることから、さまざまなマルチタスクを可能にする技術に発展しそうです。
記事を読む

動物の精子を長期間にわたって保存するためには特別な装置が必要です。しかし山梨大学の研究グループは、マウスの精子を1年以上も机の引き出しの中に入れたまま保存できる方法を考案しました。
記事を読む

「ドラゴンボール」では、主人公の悟空が戦闘能力を高めるために通常の10倍も大きな重力を受ける重力室(精神と時の部屋)で修行をします。中央大学の研究グループは、実際に過重力環境をつくると運動学習能力が高まることを実験で確認しました。
記事を読む

妊娠中に母親が喫煙をしていたり生後の受動喫煙があると、生まれてくる子どもの聴覚発達が悪影響を受ける可能性が指摘されています。妊娠期や幼い子どもがいる家庭ではとくに禁煙を促す必要性が確認されたとしています。
記事を読む

サイコパスは平然と嘘をつくとされていますが、その背景にある心理学的なまたは神経科学的なメカニズムは明らかにされていません。今回、囚人を被験者とした実験でサイコパスのメカニズムを解明する研究が発表されました。
記事を読む

日本列島や東南アジアから出土した人骨のゲノムを解析する研究から、日本人の由来に関する有力な知見が得られたようです。約2千年前の日本で生きていた女性と最も似ていたのは、現在の「ラオス」に8千年前に生きていた人だという。
記事を読む

日産自動車と産業技術総合研究所が共同で、自動車の運転において「ペダル操作」の違いがどのように脳と心に影響を与えるかについての実験結果を発表しています。
記事を読む
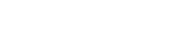

































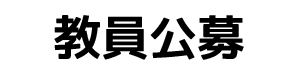
 速読力をアップする方法
速読力をアップする方法
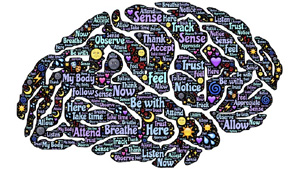 脳力をアップする方法
脳力をアップする方法
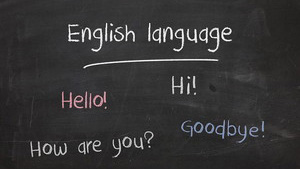 英語力をアップする方法
英語力をアップする方法